命を守るはずの情報が届かないという現実
地震、津波、台風、火災――日本は自然災害の多い国です。そのため、災害発生時に速やかに正確な情報を得ることは、私たちの命を守るうえで非常に重要です。テレビやラジオの緊急放送、防災無線、サイレン、避難勧告のアナウンスなど、災害情報の多くは「音声」を通じて伝えられます。
しかし、聴覚に障害をもつ人々にとって、こうした音による情報伝達は大きな壁となります。「逃げ遅れたらどうしよう」「情報がわからないまま取り残されるのでは」――災害時の不安と恐怖は、健常者とは比較にならないほど深刻なのです。
本記事では、聴覚障害者が直面する災害時の情報格差とその背景を掘り下げ、命を守るための具体的な対策やテクノロジーの活用方法について考えていきます。
災害時、聴覚障害者が直面する「見えない壁」
● 防災無線や緊急放送が聞こえない
自治体が屋外スピーカーで流す避難指示、防災無線、消防車やパトカーのサイレンは、視覚に訴える要素が少なく、聴覚障害者には届きません。地震直後や大雨・土砂災害発生時など、命に関わる情報が即時に届かないのは深刻な問題です。
● 避難所での案内が理解できない
避難所に到着しても、「どこに行けばいいのか」「何を持っていけばいいのか」といった指示が口頭のみで伝えられることが多く、混乱や不安を引き起こします。情報を聞き逃してしまうことで、生活物資の配布や健康管理のサポートを受け損ねることも。
● SNSやテレビに字幕がないケースも
災害時に頼りになるテレビの速報やネット配信も、リアルタイムで字幕対応していない場合があり、画面上の情報だけでは理解が難しいこともあります。またSNSでは画像や動画に音声説明だけが添えられている場合も多く、情報取得に偏りが出てしまいます。
解決策:命を守る「音に頼らない災害対策」
■ 視覚・振動による通知の活用
- 光・振動で知らせる防災機器:警報装置や火災報知器にフラッシュライトやバイブ機能をつけることで、音を視覚・触覚情報に変換
- スマートフォン連携:地震速報や緊急警報を画面表示+バイブで伝えるアプリ(Yahoo!防災速報、特務機関NERV防災など)
■ 地域社会での「共助」体制づくり
- 近隣住民による声かけ:「耳マーク」などで聴覚障害者であることを周囲に伝え、災害時の助け合い体制を構築
- 福祉避難所の整備:筆談対応や手話通訳、配慮のあるスタッフがいる避難所の存在を周知
■ 行政・メディアの情報保障
- テレビのリアルタイム字幕対応:災害発生時には自動字幕や要約筆記者による同時表示が求められる
- 文字情報付きSNS配信:災害情報の投稿には画像・音声だけでなく文字での補足説明を添える
結論:音に頼らない災害対策は、すべての人を守る備えになる
災害時の情報格差は、命に関わる重大な課題です。聴覚障害のある方にとって、「聞こえない」ことで逃げ遅れるリスクは常につきまといます。しかし、そのリスクは、社会の工夫とテクノロジーの活用によって大きく減らすことができます。
重要なのは、「音声以外でも伝える」ことを前提にした防災体制を構築すること。光、文字、振動、そして人と人とのつながり――これらを組み合わせることで、聴覚障害のある方も、そうでない方も、すべての人が安心して避難できる社会をつくることができます。
防災は“備え”がすべて。だからこそ、「聞こえない人」の視点を取り入れた災害対策は、私たち全員の命を守るための基盤となるのです。
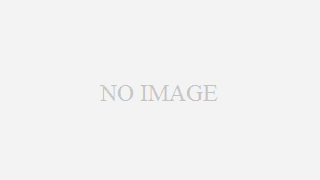

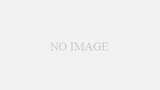
コメント