誰もが利用する場所にも、気づかれない壁がある
コンビニでの支払い、スーパーでのレジ対応、カフェでの注文――買い物は私たちの生活に欠かせない日常行動です。短時間で完結し、特別な配慮が不要と思われがちなこれらの場面。しかし、聴覚に障害がある人にとって、買い物の場は意外にも多くの“小さな困難”に満ちています。
「声をかけられたのに気づかなかった」「聞き返したら不機嫌な顔をされた」「注文が通じたか不安になる」――こうした経験は、単なる一時的な不便ではなく、日常の中で当たり前に感じる「心のストレス」に変わっていきます。
本記事では、聴覚障害者が買い物時に感じるバリアと、店舗側や社会ができる配慮のあり方を、具体例とともに考えていきます。
レジ・注文時に起きるコミュニケーションのすれ違い
● 「ポイントカードは?」「袋は?」の声かけが聞き取れない
レジで当たり前のように飛んでくる声かけ。しかし聴覚障害者にとっては、いきなりの質問に気づけず、返答できなかったことで気まずい空気になることも。「無視された」と誤解されてしまうケースも多くあります。
● 飲食店での注文が不安
店員に口頭で注文する形式の飲食店では、聞き返したくても混雑時には気が引ける、店員がマスクをしていて口元が読めない、といった理由で正確なやりとりが難しくなりがちです。結果として「伝わったか不安」「違うメニューが出てきた」といったトラブルに発展することもあります。
● セルフレジや自動音声の壁
近年普及しているセルフレジや自動音声案内は、便利な一方で、聴覚障害者には「何を求められているのか」がわからず操作が難しいという新たなバリアになっている場面もあります。
解決策:誰にとってもやさしい「買い物体験」へ
■ 視覚的サポートの強化
- レジ画面での表示強化:「ポイントカードはお持ちですか?」「袋の有無」などを画面上で確認できるようにする
- タブレット注文・券売機の導入:口頭注文を減らし、文字ベースで注文が完了できる設計が効果的
- 音声に頼らない操作ガイド:セルフレジでも音声だけでなく、視覚的な指示や点滅などの工夫が必要
■ 筆談・ジェスチャーの受け入れ体制
- 筆談用メモパッドの常備:レジや受付でさっと出せるようにしておくと安心感がある
- スタッフへの研修:簡単な手話や指差しコミュニケーションの対応を学ぶことが、トラブル回避につながる
- 「筆談対応します」などの掲示:障害の有無に関係なく、誰でも安心して利用できる空間づくりに
■ 利用者側の工夫と社会の理解
- 「耳マーク」「手帳提示」などで意思表示:店側に気づいてもらいやすくなる
- チャット注文・事前オーダーアプリの活用:最近ではアプリを使って静かに注文できる飲食店も増えている
- 周囲の一言:困っていそうな人に「お手伝いしましょうか?」と声をかけることが大きな助けに
結論:小さな配慮が、安心して買い物できる社会をつくる
買い物とは、誰もが毎日のように経験する、ささやかな社会参加のひとつです。その中にバリアがあるということは、日常の安心や尊厳を脅かされることに直結します。
「聞こえない」ことで不安を感じたり、誤解されたりすることのない社会――それは、聴覚障害者にとってだけでなく、すべての人にとって“利用しやすい社会”をつくることにつながります。
ほんの少しの工夫、ほんの少しの思いやりが、買い物という日常を大きく変えていくのです。
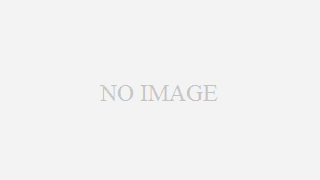

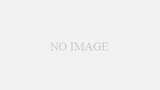
コメント