“見えない”からこそ、見過ごされる
聴覚障害は、車いすや白杖とは違い、外見からは障害があることが分かりにくい特徴を持っています。そのため、本人が困っていても、周囲からは「普通に見える」「なぜ反応しないのか分からない」と誤解されやすくなります。
「呼んでも無視された」「話が通じない」「空気が読めない」――そうした心ない言葉が、聴覚障害のある人にとってどれほど大きな傷になるか、想像できるでしょうか。
本記事では、「見えない障害」である聴覚障害が社会の中でどう捉えられてきたのか、その特性と向き合うために社会全体がどのような視点を持つべきかを考えていきます。
見えない障害が生む“誤解と無理解”
● 障害に気づかれず、配慮されない
困っていることがあっても、「健常者に見えるから」と支援の対象とされなかったり、手助けの声がかけられなかったりすることがあります。目に見えないがゆえに、支援から取り残されてしまう現実があります。
● 「健常者と同じように振る舞え」とされるプレッシャー
聞こえないことを知られていないがために、普通に対応できるはずと期待され、会話や行動のズレを「不自然」「協調性がない」と評価されてしまうこともあります。これは、当事者の自己肯定感を大きく揺るがします。
● 言い出しにくさが孤立を生む
「自分が聴覚障害者である」と伝えることに、強い抵抗や不安を抱える人も少なくありません。「迷惑をかけたくない」「理解されないかもしれない」という思いから、サポートを求められず、一人で抱え込んでしまうのです。
見えない障害を“見える化”する社会的工夫
■ 視覚的に伝える「マーク」や「サイン」
- 耳マーク:聴覚障害を周囲に伝えるシンボルマーク。名札や持ち物に付けることで配慮を促せる。
- ヘルプマーク:援助や配慮を必要としていることを知らせるための共通表示。
- スマホ画面での事前表示:接客前に「聞こえません」と伝えるデジタルカードなどの活用。
■ 情報保障のある環境整備
- 文字情報の徹底:音声だけでなく、文字で情報提供を行う(案内板・掲示・字幕など)
- 筆談やチャット対応の導入:病院、役所、店舗などでの導入が進んでいる
- 手話通訳者・要約筆記者の派遣制度活用:公共機関や教育現場でのサポート体制強化
■ 一人ひとりの「気づく力」
- 違和感を感じたら、まずは尋ねてみる:「何かお困りですか?」という一言が大きな助けに
- 多様な人がいる前提で接する:すべての人に伝わる言い方・伝え方を日頃から意識する
- 「配慮する」ことが特別ではない社会へ:誰にとっても暮らしやすい社会は、すべての人にやさしい
結論:“見えない障害”に、見える理解と共感を
聴覚障害は、その外見からはほとんど気づかれません。だからこそ、困っていても周囲から配慮されにくく、誤解されやすいという特徴を持っています。これこそが“見えない壁”の正体です。
大切なのは、特別視することではなく、「見えないかもしれない困難がある」ことを、常に意識しておくこと。そして、ちょっとした想像力と行動が、当事者の安心と尊厳を守る第一歩になるのです。
“見えない障害”に、見える理解と共感を。そうした小さな積み重ねが、誰もが生きやすい共生社会の実現につながっていきます。
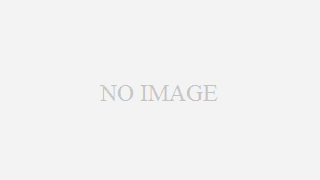

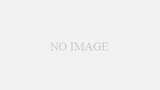
コメント