聞こえないことで、命に関わる医療ミスが起こる
病院とは、命を守る場所であり、正確で丁寧なコミュニケーションが最も求められる場所です。しかし、聴覚障害のある人にとって、医療現場は決して安心できる空間とは限りません。
診察の呼び出しに気づかない、症状がうまく伝わらない、医師の説明が理解できない――。こうしたコミュニケーションの断絶は、時に誤診や服薬ミスといった重大な医療事故を引き起こす可能性もあるのです。
本記事では、医療機関で聴覚障害者が直面する問題と、その原因、そして命を守るために必要な「合理的配慮」やテクノロジーの活用方法を具体的にご紹介します。
医療現場で起こっている「聞こえないリスク」
● 診察の呼び出しに気づけない
病院の待合室では、名前が音声で呼ばれることが多く、聴覚障害者は気づけずに診察の順番を逃してしまうことがあります。「呼んだけど来なかった」と医師や看護師から誤解されるケースもあり、不当な扱いを受けることも。
● 症状説明や病状説明が伝わらない
自分の症状をうまく伝えられず、医師の説明が聞き取れないことで、病状の理解に差が生まれます。「なんとなく分かったふりをしてしまった」「説明された薬の飲み方が違っていた」など、命に関わる誤解が起こりうるのです。
● 同意が正しく得られない“危険な同意書”
手術や検査の同意書に署名する際も、説明が口頭のみだと十分に理解できないまま同意してしまう可能性があります。これは「インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)」の原則を大きく損なう深刻な問題です。
解決策:安心して医療を受けるために必要な配慮
■ 視覚と文字を活用した情報伝達
- 診察券に「聴覚障害あり」と明記:スタッフ間で共有され、事前に配慮しやすくなる
- 振動式・番号表示の呼び出しシステム:視覚と振動で呼び出しに気づける環境を整備
- 医師の説明を紙やタブレットで提示:手順や注意事項は文字で残すことで誤解を防ぐ
■ 手話・筆談によるコミュニケーション保障
- 手話通訳者の派遣:事前予約制で、病院側が手配できる自治体制度もあり
- 筆談ボードや電子メモパッドの常備:対面でのやりとりをスムーズに
- 簡易手話や指文字の活用:医療スタッフが最低限の手話を覚えることも有効
■ ICTツールの活用
- 音声文字変換アプリ(こえとら、UDトークなど):リアルタイムで医師の説明を文字化
- 動画付き医療説明資料:字幕付き動画で検査や服薬方法を説明
- チャットやLINEによる事前問診:電話ではなくテキストベースでのやり取りを可能に
結論:聞こえることが前提の医療から、誰もが安心できる医療へ
医療は「聞こえる人」だけのものではありません。聴覚障害のある人にとっても、適切な治療と安心できる説明を受ける権利があります。だからこそ、病院・クリニックなどの医療機関は、“聞こえない人にどう伝えるか”を常に意識し、実践していく必要があります。
情報を文字で伝える、手話通訳を手配する、筆談を快く受け入れる――そうした配慮が一つずつ積み重なることで、「聞こえない医療」は「伝わる医療」へと変わっていきます。
そして何より重要なのは、「理解しようとする姿勢」です。耳が聞こえなくても、医師との信頼関係を築くことはできます。命を守る現場だからこそ、そこにいるすべての人が、正しくつながれる社会を目指しましょう。
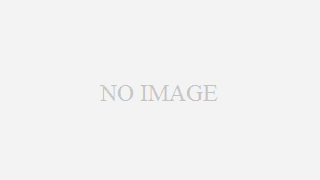

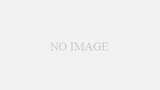
コメント